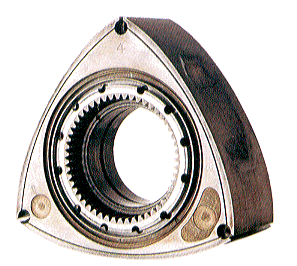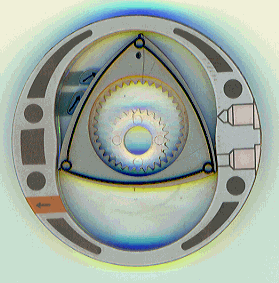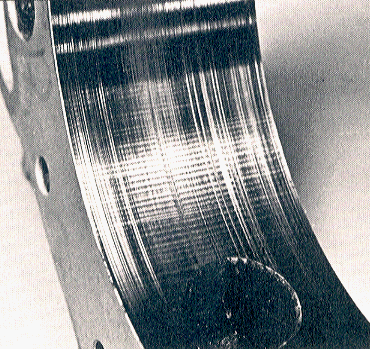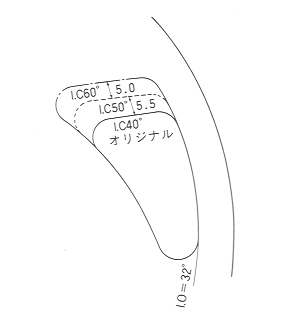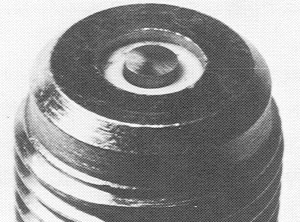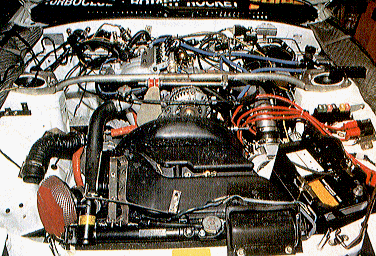ロータリーエンジン,その独特のフィーリングとは?
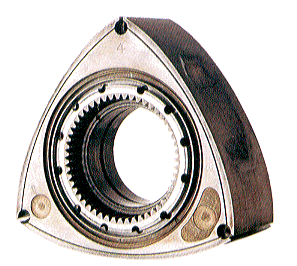
往復運動ではなく、純粋な回転運動によるエンジンは出来ないものか?そんな発想から生まれたロータリエンジン。
フェリックス・バンケルが発明した、その基本構造は世界で唯一マツダ製の車両に搭載されて生き続けている。
現在実用化されているロータリエンジンは、完全な回転運動ではない。
エキセントリックシャフトと言う、レシプロエンジンのクランクシャフトに相当する変心したシャフトを軸に回っているのだ。
フェリックス・バンケルの考案した最初の形態は、完全な円運動を実現したものだ。
その為には、ロータハウジング(上の写真のようなおむすび型ロータを納めているまゆ型のハウジング)とロータを3:4の比率で同方向に回転させるものだった。
しかし、それでは構造が複雑になりすぎて実用化できるものではなく,エキセントリックシャフトを使用してロータハウジングを固定する方法で現在に至っている。
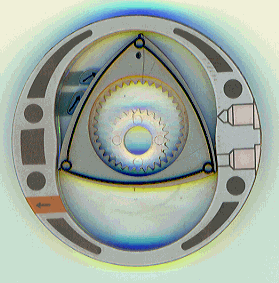
これは、マツダでもらった模型。
右側に2本の点火プラグが見える。
左側が吸気と排気のポートである。
この機構がどんなふうに回るか?この模型を徐々に回転させながらでないと説明しにくいが、AVIやアニメーテッドGIFを作る根性がないのだ。
でも、Furuichi's
Worldに行けば見られるよ。
おむすび型ロータの頂点にガスシール(アペックスシール)がある。
エキセントリックシャフトを使用する方式にしたため、アペックスシールにかかる荷重は不連続なものとなり、その為に重大な問題を発生した。
シールが共振してロータハウジングとの摺動面に傷を作るのだ。
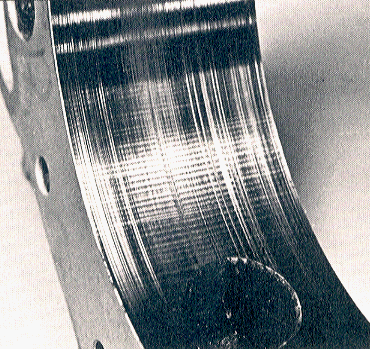
この対策として、アペックスシールの改良に次ぐ改良が重ねられた。
最初は全くの手探り状態で、金属からカーボン、挙げ句の果てには牛の骨まで使用したというのは有名な話。
そのかいあって現在のエンジンは、激しくチューニングされたものをバラしてみてもチャッターマーク(傷)はほとんど見られない。
ロータリエンジンのチューニング
ターボが登場する以前は、ポートタイミングを変更してパワーアップを図るものが殆
どだった。
ノーマルではサイド吸気のインテークポートを,排気と同じペリフェラルポートとして吸入効率の改善を図った方式は、レーシングカーでおなじみのものだった。
この方式では、654cc×2ロータのエンジンから300馬力以上を出力することが可能だ。
しかしオーバラップが広がるため、アイドリングはバラつき低速トルクはなくなるのでとても町中での使用が出来るような代物ではない。
そこで、より安定志向のポートチューニングを行うことになる。
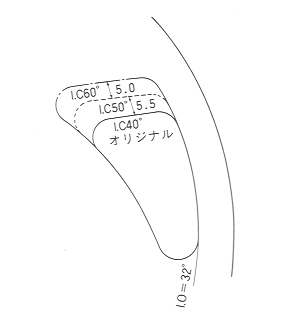
これは、インテークポートを示したもの。
I.Cはインテーククローズ、I.Oはインテークオープンを示す。
I.Oを早めたいところだが、これ以上削るとアペックスシールがポートに落ちてしまうのだ。
従って、クローズ側を拡大して吸気効率改善を目指すしかない。
しかしターボが登場した今、ポートチューニングはずいぶん減ったと思う。
ターボチューンならエンジンに手を加えず、ノーマルの2倍以上の出力が出せるからだ。
現行RX−7(FD3S)なら、ノーマルタービンでも400馬力近くをマークする。
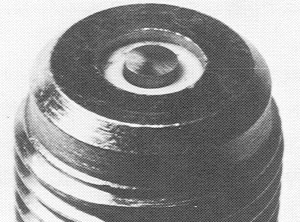
ロータリには点火性能も重要だ。
通常のエンジンは、50mJ(ミリジュール)も有れば十分点火できるが、ロータの回転とともに燃焼室が移動してその形状も変化するロータリでは、おそらく100mJ以上の点火パワーが必要だと思う。
何しろノーマルでさえ2本の点火プラグが付き、レース用に至っては3本プラグを採用する例もある。
上の写真のように沿面電極プラグ(主にレース用)を使用するのは、接地電極の陰になって点火しにくくなることを防ぐためと、コールドタイプの熱価の両方の要求が満たせるからである。
点火性能強化策としてCDIが使用されることもあるが、レーシングユースならともかく町乗り用としては問題もある。
CDIは点火電圧自体は高いものの、放電時間が短いため低速域での性能劣化が発生するからだ。
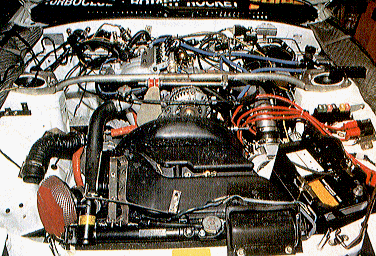
ターボチューンの場合油温の上昇に気を使ってほしい。
ローター内部の冷却はエンジンオイルの仕事なのだ。
また、燃調に関してだがロータリーは燃料が濃すぎても壊れる。
これは、ロータハウジングとロータを潤滑しているオイルが燃料によって洗い流されてしまい、十分な潤滑作用が維持できなくなってしまうから。
谷田部で聞くロータリサウンドは独特のものがある。
RX−7は空力特性が良いので、風切り音より、エキゾーストノイズが目立つのだ。
300Km/h近い速度でストレートを通過する姿は迫力だよ!