スマートフォンの値引き規制を回避するため、ソフトバンクは下取り額を高く設定した。
実質価格は新品価格から下取り額を減じたものになるので、下取り額を高くすれば実質価格が下がる。
そして下取り価格を高くするために、買い換えまでの期間を1年と短くした。
他にもトリックがあるのだが、こうした抜け道によって安価にスマートフォンが使える仕組みが出来た。
勿論高く下取ったものがその価格で売れるわけではないので、見えない部分での値引きが行われている事になるが、事業者がいくらで買い取るかは事業者任せだ。
買い取りの原資は通信料金になるので、ソフトバンクはいち早く値上げに転じたと言う事だ。
これに対して総務省は、下取り額の公平性・透明性を上げる事を行う。
これによって事業者が好き勝手に下取り相場をコントロールする事は出来なくなる。
総務省案に反対するのが石川氏で、氏は値引き規制にも反対している。
まあApple関連と言う事で、中々自由な事は書けないのかも知れない。
値引き規制が良いのかどうかは意見が分かれるところだ。
石川氏のように通信料金が上がってもスマートフォンが安くなった方が良いと考える人もいる。
従来型携帯電話の時代から、新規加入者優遇のために既存加入者が損をしていると言われ続けてきた。
その一つの解決策が分離プランと値引き規制であり、これによる通信料金の値下げだった。
しかし自由競争の中で、政府が値引きをコントロールするのが良いのかという根本的な問題はある。
MNOの通信料金が高くなれば、より安価なMVNOに人々は移るだろう。
ただし回線の卸価格に加入者獲得費用が乗せられれば話は別で、MVNOも値上げせざるを得なくなる。
分離プランと言いながら、結局は分離できないところが問題なのだ。
第一次分離プランはソフトバンクにぶち壊され、そして今もソフトバンクが法の抜け穴を見つけた。
こうした動きがある以上、分離プランを推進する総務省が動くのは当然とも言える。
料金の許認可方式など他の事業のようにする事は不可能ではない。
或いは発送電分離のように、インフラ会社と運用会社を別にする方法もある。
ただこうして政府が絡むごとに、関連企業や団体などの天下り先が増えていく。
携帯電話料金の議論も大切ではあるが、携帯電話会社のエネルギ使用量が通信価格にも当然響いている。
今や世界一高いと言われる日本の電力単価、単純比較で米国や韓国の3~4倍、物価換算比較だと米国の10倍とも言われる。
電力料金を下げれば全ての価格が下がり、国際競争力が高まる。
今や中国都市部よりも安いと言われる日本の人件費なのだが、エネルギコストや輸送コストが高く、結果として競争力が弱まっている。

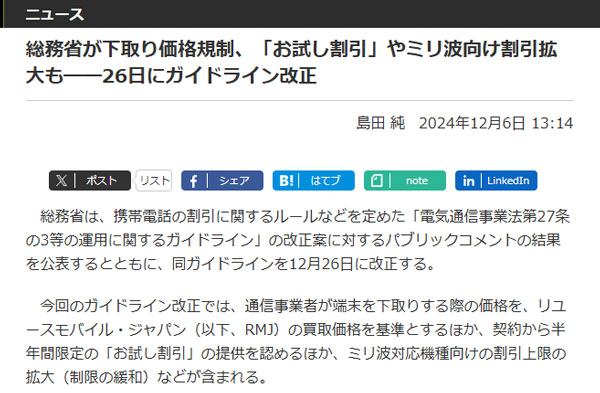
コメント