ふるさと納税ポータルサイトでのポイント付与が禁止された。
楽天は不服として行政訴訟を起こしている。
そもそも付与されるポイントの原資は何かと言えば、それはふるさと納税を受ける自治体の予算、すなわち税金である。
例えば楽天の場合、出店費用に加えてバナー広告費用、メルマガ費用、ポイント付与費用、アフィリエイト負担分、Edy利用料などなどを取られる。
広告費やメルマガ費用は固定的なものだが、売り上げに応じて加算される手数料もある。
Edy支払い費用は馬鹿高くて、(当時)700円だったかな。
しかしEdy支払いを禁止する設定はないので、Edyで支払われたら出店者権限で注文をキャンセルした方が良いと言われた。
ふるさと納税では金券などの返礼は禁止されている。
このきっかけになったのが大阪府泉佐野市ふるさと納税事件(令和2年(行ヒ)第68号 不指定取消請求事件 令和2年6月30日第三小法廷判決)で、2018年度には497億円以上のふるさと納税を集めたが、返礼品としてAmazonギフト券が360億円を占めた。
換金可能なギフト券で返礼をするという事は、納税額と返礼額の差の137億円を集めたと考えられるが、一方では497億円分が税控除の対象となるのだから財務省が黙っているわけがない。
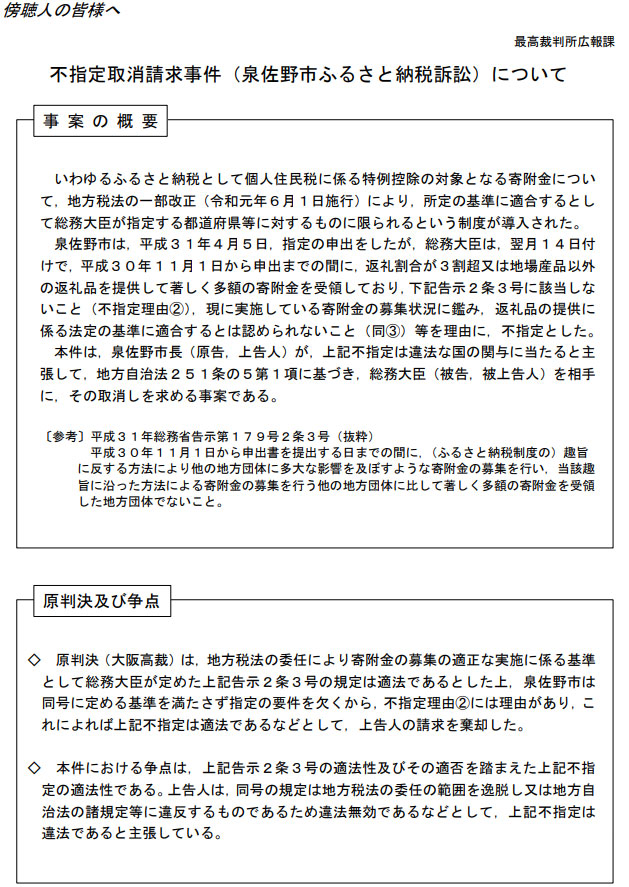
この理屈で行けばポイントも換金可能な金券同等という事になるので、制限されるのは当然と言える。
現在は以下の規定がある。
・返礼品は地場産品であること。
・寄付金額の3割を上限とすること。
Amazon日本支社を誘致すれば、Amazonギフト券は地場産品になるのかな?
えーと、造幣局は大阪だったっけ。
換金率に差があるとは言え、全ての物品は換金が出来る。
返礼品をメルカリに出品している人は多いわけだから、だったら換金可能な返戻金でも同じじゃないかと言いたくもなる。
楽天が怒り狂っているのは、ふるさと納税ポータルの運営が大きな利益を上げるからだ。
各自治体はふるさと納税ポータルの選定に、入札を行っているのだろうか?
返礼は3割を上限としているが、実際にはポータルに取られる費用もある。
ではポイント付与の禁止でポイントが付与出来なくなるかと言えばそうとも言い切れない。
携帯電話の分離プランを進める総務省に対して、何が何でもインセンティブを出すというソフトバンクとの戦いのようなものだ。
例えばふるさと納税を楽天Payで払えば20%還元とやれば、これはふるさと納税ポータルで還元しているのではなく、あくまでもコード決済で還元していることになる。
勿論それは自治体に請求されるわけだが、表向きはサイト利用料とかキャンペーン費用という形になる。

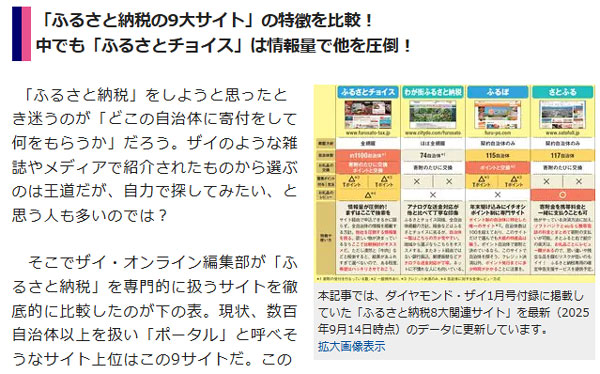
コメント