ミニのオイルを交換した。
今回は5千kmを少し超えるくらい走ったかなと思って記録を見たら、約4千kmしか走っていなかった。
前回交換してから半年が経過している。
ジムニーにはTRIP A/Bがあるのでオイル交換時にTRIP Bをリセットしておくのだが、何かの整備でバッテリーを外してリセットされちゃったとか、オイル交換時にリセットを忘れたとかで、半年経ったら交換みたいな感じだった。
ミニはオイル交換のアラートが表示されるのだが、1.5万km(走行状態によって変化する)にセットされているので役に立たない。
どこかの設定で変えられる、みたいな話は聞いた事があるが、いわゆるコーディングではなくVOの書き換えが必要なようだ。

オイル交換と同時にオイルフィルタも交換する。
オイルフィルタの蓋の部分にはドレンプラグが付いていて、そこを外すとオイルフィルタハウジング内のオイルが抜ける。
オイルフィルタハウジング内のオイルを抜けば、オイルフィルタを外すときにオイルがこぼれない。
オイル交換はアンダーカバーの蓋を開ければ良いのだが、点検もかねてアンダーカバー自体を外す事にしている。
アンダーカバーを外すとオイルフィルタからオイルが漏れてもオイルパンに付着する位なので、オイルフィルタキャップのドレンプラグは開けないでそのまま外してしまう。
上の写真の右の方にあるのがオイルフィルタと、オイルフィルタハウジングのキャップだ。
オイルフィルタキャップのOリング、ドレンプラグは再使用禁止。
オイルフィルタを買うとこれら交換部品が付属してくるが、ドレンプラグは交換しないのでいくつか溜まってきた。
オイルパンのドレンプラグのワッシャも、オイルフィルタを買うと付属してくる。
国内ではHU6015ZKITとして、Oリングや銅ワッシャの付いたものが売られているが、海外ではこれらの付属しないフィルタのみも売られている。
米国Amazonで見ると$81.4って、1桁間違ってない?
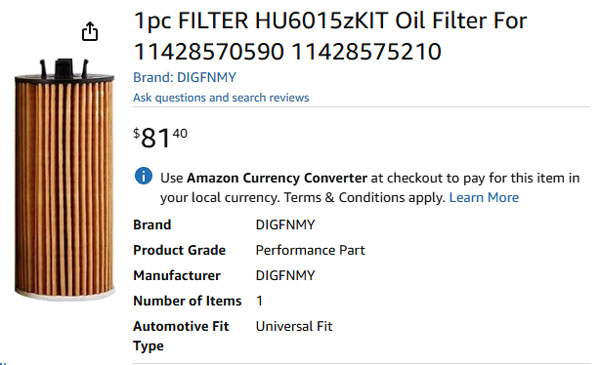
Amazon.deだとMAHLEでもMANNでも13ユーロくらいだ。

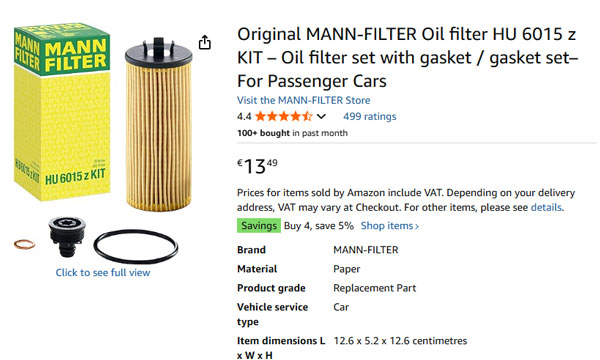
米国でやたら高いのってトランプ関税の影響?
それにしても価格が高すぎるなぁ。
フィルタは使ってしまったら買うことにしているので、今回も又MANNのものを発注しておいた。
前回購入したときより300円位安かった。
オイルはジョッキで入れるのだが、今は蓋付きのものを使っている。
以前は蓋のないものを使っていたのだが、蓋がないと少なからず埃が入るので一々洗浄していた。
用途や使用頻度にもよるが、アマチュアが使う分には蓋付きの方が良い。
オイルジョッキはミニ用とスクータ用で分けているので、オイルが混ざる事もなく、一々洗浄はしなくなった。
オイル交換後はライトで照らしながら一通りの点検、オイル漏れも冷却水漏れもグリスの飛び散りもなかった。
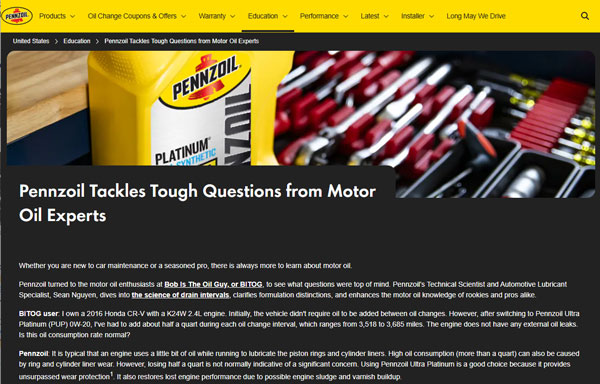
現在はMOTUL 8100を使っているのだが、PENNZOIL PLATINUM EUROを使ってみたいと思った事があった。
PENNZOILは米国の企業でオイルのシェアは大きい。
2014年頃からベースオイルを原油からではなく天然ガスから作っているが、これはShellのGTL同様である。
2020年頃から欧州でプロモーションを開始し、販売量を増やした。
この頃から比較テストや成分分析記事が増え、欧州での知名度が上がった。
日本でも2~3年前からプロモーションを強化して、取扱店が増えている。
ただ日本で並行輸入物を扱っている某社がどうにもうさん臭い。
販売しているのは整備工場か中古車販売店なのかな。
この販売店の言う事もアレなのだが、並行輸入業者もかなり怪しい。
まあ商売だから売りたいのは山々というか、ある程度のオカルト話は仕方ないのかなとは思うのだが…
販売店によれば、日本正規品はオイルによる密封作用がないのだそうだ。
並行ものは本物で、日本の正規ものは性能が悪いので1,000kmごとに交換しなければダメだとも言っている。
PENNZOILだけではなく日本製のオイルは全てダメ、成分分析すればすぐに分かると力説するも、成分分析の結果は示さない。
米国には存在しないオイルというかグレードのものを並行輸入品として売っているのだが、これってどこから持ってきたのだろう?
並行ものは米国から買っているから、これ以上の本物はないと言っていたが…
実は米国内での販売品が他国産だという事が分かったりして、それは産油国が他国であって精製は米国だから良いとか何とかと、だんだん訳が分からなくなってくる。
だったら日本の国内正規ものはどうなの?
更には米国から輸入しているものはアプルーバルが取れていない(日本正規販売品は取得済み)事が露呈した。
並行輸入業者※は以前はPENNZOILとして売っていたものを、(中身は変えずに)オリジナルブランドに変えた。
中身はPENNZOILだがパッケージを変え、「米国製PENNZOILのOEM商品です」として販売している。
これって逆に考えると、(以前は)適当なオイルをPENNZOIL(に似た)缶に入れて売っていたなんて事はないのだろうか?
PENNZOILはグループIIIな筈だが、この輸入会社が販売するPENNZOIL的ものはグループIIだそうだ。
もう何が何だか分からない。
以前にも書いたがEARL’Sを輸入販売していた企業が、オリジナルを真似て作ったものを本物と混ぜて売っていた。
ライセンス生産ではなくコピーである。
こうした事もあって日本におけるPENNZOIL=怪しいと思う人が増えた。
こうなると日本正規品に怪しげなコピー品が混じっている可能性もあり、輸入会社では既に整備工場向けにオリジナルブランド品をPENNZOILとして(オリジナルパッケージで)納入していると言っている。
最近は通販でもオリジナルパッケージ入りのPENNZOIL的ものを売っている。
SHELLも色々困っているようだ。
一部には日本版PENNZOILの販売を中止するなんて噂もある。

儲かるところに何やら怪しい人が群がった、みたいな感じかな。
オイルは仕入れ値が安く儲かるので、昔からこうしたブローカ的な人たちが蠢(うごめ)いている。
| PENZOIL 5W-40 | 20リットル | Approval |
| 米国Amazon | 約1.4万円 | 主に米国車、日本車 |
| 日本Amazon | 約1.8万円 | 主に欧州車 |
| 並行業者 | 約7.2万円 | 取得していない |
| OEM品と称するもの | 約3.5万円 | 取得していない |
個人的にPENNZOILが悪いものだとは思わない。
日本代理店は株式会社レッドアンドイエローで、シェルグループだ。
つまり日本ではシェルグループがPENNZOILを作っていると考えることが出来るし、Approvalも取得しているのだろう。
PENNZOILを作っていると思われるSHELLのHelix ULTRA EUROも悪くない。
製法的にはGTL(天然ガスベース)で、コストメリットを出しやすいのかな。
SHELLは日本では一般販売していなかったのだが、系列スタンドの統廃合で販売ルートを変えたとか。
石油会社系ではMobil 1™ FS X2の品質が高いと言われていて、各種テストでも常に上位に入っている。
Mobile1も一度使ってみたいのだが値段が高い。
しかし近年MOTULの値上がりが激しいので、Mobile1との価格差が減少した。
なおMobile1でも粘度によってGroupIII+だったりGroupIVだったりする。
以前は0W-40がPAOベースだったが、今はVHVI+GTLになっている。
レーシング用として発売されているものはPAOベースがあるのだが、潤滑性確保のためにモリブデンと亜鉛系添加剤が多く含まれているので、ストリートユースには向かない。
BMW純正オイルの中身は(今は)SHELLだったかな。
GTLベースのオイルは動粘度指数が高く、純度を上げるコストが低い(元々不要成分が少ない)メリットがあるという。
GTLを使っているのはSHELLとMobile1だけだと思う。
| ベースオイル | 製法他 | |
| MOTUL 8100 X-CESS gen2 | Group III Hydrocrack | hydrotreated heavy paraffinic 50%~100% |
| MOBILE1 FS X2 | Group III+ | severely hydrotreated heavy paraffinic distillate/GTL |
| SHELL HELIX ULTRA EURO | Group III GTL/Hydrocrack | VHVI+GTL |
| PENNZOIL | Group III GTL | GTL |
VHVIなど水素化精製成分が50%以上のものはGroup IIIに分類されているので、化学合成成分51%と鉱物油49%でもGroupIIIを名乗れて化学合成オイルになる。
GTLは鉱物油ではないからGroupV(あるいはPAO同様)だとする人もいるが、現状ではGroupIII分類になる。
GroupIIIの化学合成オイルだとPAOやエステルなどを添加剤として入れるので、成分だけでの判断は難しい部分もある。
エステルベースのオイルもあるが、どうしても価格が上がってしまうので需要が限られる。
エステルは吸水性や安定性の問題もあり、添加量も各オイルそれぞれだ。
添加剤までは書かれていない場合が多いが、SDSを見るとベースオイルは分かる。
普通はSDSが公開されているが、内容の詳しさはそれぞれだ。
オイルのデータはオイルの仕様みたいなものなので、少なくとも物性は分かるようになっている。
WAKO’sの一部オイルは問い合わせても非公開の返答が来るとの記事があった。
未確認情報なのだが、WAKO’sがGroupIVを名乗る銘柄の添加剤成分が鉱物油で、これの配合割合が多いので(本来は)GroupIIIになってしまうとか何とか。
TAKUMIモーターオイルもSDSが公開されていないので、謳い文句を信じる以外にない。
PAOは生産量が少なく価格が高いので、従来はPAOベースのGroupIVだったオイルが、HydrocrackのGroupIIIに変わったものもある。
また同じ銘柄でも粘度によって配合が異なるので、何ともややこしい。
高度水素化精製鉱物油・高度精製鉱物油ベースのオイルを化学合成と名乗らせてしまったカストロールの罪とも言える。
もっともそのおかげでMobile1もPAOベースではないオイルを化学合成としているわけだけど。
今や数少ない存在となったGroupIV PAOベースでもっとも安価なのはAZのCER-001/RACINGだ。
企業方針として認証は取らない(認証コストをかけず、オイルを安く販売したいとのこと)そうだ。
MOLY GREEN PERFECTもPAOベースなのだが、現在販売されていない。
某整備工場の記事で、どんな時にエンジンオイル交換が必要か?
また、エンジンから「カタカタ」や「ガラガラ」といった金属音が聞こえるようになり、これはオイルの潤滑性能低下によりエンジン内部の金属部品が直接こすれ合い始めている危険信号です。
いや、これって壊れてるでしょ、既に。
※2022年に設立され、従業員は4名だそうだ。
親会社(代表者は同じ)は2009年に設立された運送会社になっている。


コメント
こんにちは!
某並行輸入業者のオリジナルブランドXHVI10w-40をここ1年使ってます。その前はPetrocanada、ワコーズPro-stage、使ってました。
現在5車種10台以上保有ししているので色々と比較してみたりしての感想ですが、
case-1)2003年式メルセデス製599ccエンジン、RR、走行距離約10万kmの場合、Pro-stageはオイル交換後1800km辺りで聞こえてくるエンジン音とエンジン振動が大きくなってましたが、オリジナルブランドXVHIは4000km走行後辺りからエンジン音と振動が大きく感じられました。この車種5台持ってましてどの車両もほぼ共通です。燃費に違いは見られません。
case-2)2011年式国産2000cc製ミニバン、FF、走行距離13万kmの場合は、たまたま片道1000kmを2往復し、Pro-stageとXVHIを交換して往復2000km走行しました。乗車人数、積載荷物量、走行時間帯、エアコン状態等はほぼ同じでしたが、エンジン音、エンジン振動はcase-1)程ではありませんがやはりオリジナルブランドXVHIの方がエンジン音、振動共に静か、小さめに感じました。燃費はオリジナルブランドXVHIに変更後1.8km/L向上が見られました。
他に感じた違いは、排出したオイルを素手で触った感覚は明らかに異なります。Pro-stageは水のように粘性が無いのに対してオリジナルブランドXVHIは粘性が残ってました。
とは言え上記感想は(燃費以外)はあくまでも感覚的なモノですし、これらの違いがエンジンに対してどのような影響を与えてるかは素人の私には不明なので「信じる者は救われる」かなと。
という状況で価格的にPro-stageとほぼ同じで交換サイクルが伸ばせそうなオリジナルブランドXVHIに今のところは不満はありません。